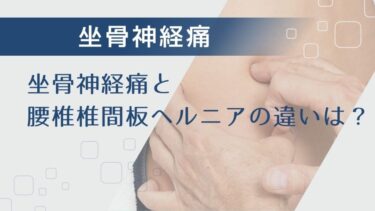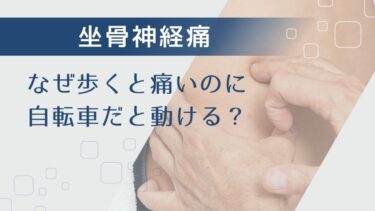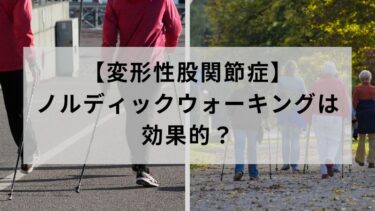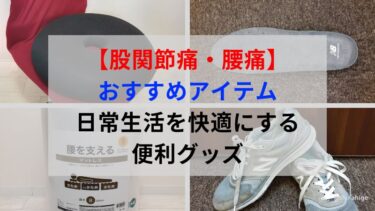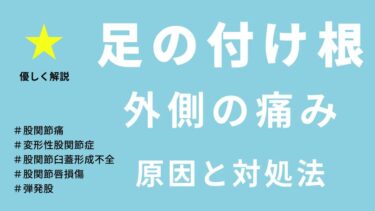- 股関節唇損傷ってどんな症状?
- 股関節唇損傷はどのくらいで治るの?手術が必要?
- 運動は続けても大丈夫?
今回は、こんなお悩み解決していきます。
股関節唇損傷のポイントは、次の通りです。
- 股関節唇と股関節にある軟骨の一種。
- 繰り返しの動作、強い負荷、臼蓋形成不全などで損傷しやすい。
- 損傷すると股関節の引っ掛かりを感じる。
- レントゲン検査では判断できない。

本記事では、股関節唇損傷の原因・症状・治療法から運動療法の進め方、日常生活の注意点などをわかりやすく解説しますので、ぜひ最後まで読んでください。
それでは、さっそく見ていきましょう。
\脱ぎたくなくなる履き心地/
通勤・買い物・旅行、ぜんぶ快適
股関節唇損傷とは?
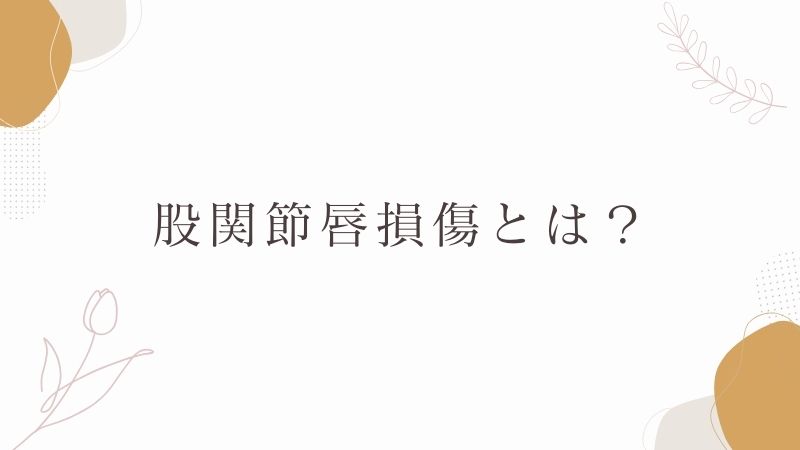
股関節唇は、骨盤の縁を囲む軟骨組織で、股関節の安定性を保つ重要な役割を担っています。
股関節唇は、関節内の圧を保ち、潤滑液を保持する「パッキン」のような働きをしており、スムーズな動きをサポートします。
しかし、スポーツや事故、繰り返しの動作、加齢などの要因で、この股関節唇が裂けたり剥がれたりすることで損傷が発生します。
損傷すると、関節内の安定性が低下し、痛みや引っかかり感を感じやすくなるのが特徴です。
股関節唇損傷の原因
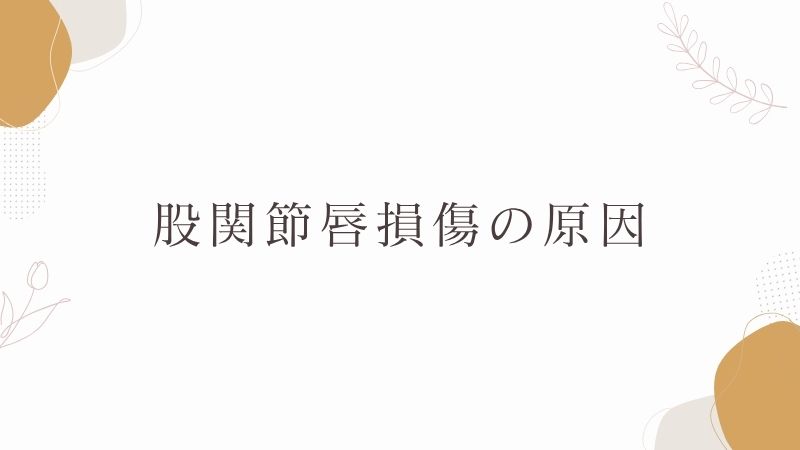
股関節唇損傷の原因には、次の通りです。
●股関節唇損傷の原因
- スポーツ
- 過去のケガ
- 構造の問題
- 繰り返しの動作
- 筋力低下
- 連鎖運動の低下
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
スポーツ
走る、ジャンプする、捻る、踏ん張るといった強い負荷が繰り返されることで、股関節唇に無理がかかり損傷することがあります。
スポーツ選手の股関節痛の約20%は股関節唇損傷が原因とされています。
過去のケガ
交通事故や転倒などの強い衝撃が損傷の原因となることがあります。
また、軽度の損傷でも時間経過とともに悪化し、痛みを感じる場合もあります。
構造の問題
股関節を構成する骨の骨盤側が成長段階でうまく形成されないのが寛骨臼蓋形成不全。
寛骨臼蓋形成不全はレントゲン検査で「股関節のかぶりが浅い」とも言われます。
股関節臼蓋形成不全では、股関節がうまくはまっていないことに加え、運動不足や柔軟性の低下により股関節に負担がかかり股関節唇にも影響を及ぼします。
股関節臼蓋形成不全ってどんな症状。 股関節臼蓋形成不全はどんな座り方をすればいい? 股関節臼蓋形成不全でやってはいけないことは? 今回は、こんなお悩みを解決していきます。 &nbs[…]
繰り返しの動作
繰り返しの動作で持続的に股関節への負担が蓄積することで、股関節唇が損傷します。
例えば、「機械のペダルを踏む」「踏み込み」など、継続的に繰り返し行うことで、股関節に負担がかかります。
筋力低下
筋力の中でもインナー筋の低下により、股関節唇損傷が起こりやすくなります。
股関節は、インナー筋によって安定を保っています。
インナー筋は「繰り返しの動作」「不良姿勢」「運動不足」などにより低下します。
連鎖運動の低下
体は連動して動いています。
例えば、階段を上るように脚を上げ股関節を曲げる動きは、「骨盤・背骨・肩甲骨・背中の筋肉」などさまざまなパーツを使います。
なので、股関節以外の体の不具合が回りまわって、股関節の負担になり股関節損傷の原因になります。
股関節唇損傷の症状
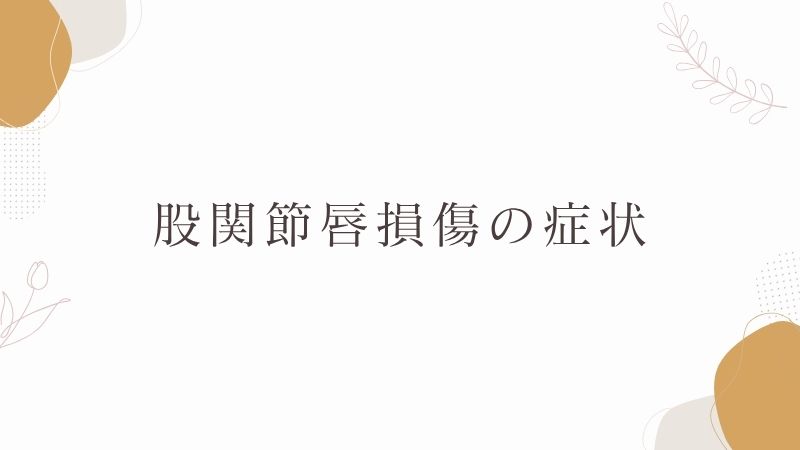
股関節唇損傷では、次のような症状が現れます。
●股関節唇損傷の症状
- 股関節の激痛を感じる。
- 動き始めに激痛を伴う。
- 股関節に引っかかりを感じる。
- 股関節がぐらつく。
- 股関節が抜けそうな感覚がある。
- 股関節がはまっていないように感じる。
股関節唇には神経が通っているため、損傷すると痛みを感じます。
また、「引っかかり感」や「抜けそうな感覚」は股関節唇損傷の特徴的な症状です。
股関節唇損傷はどうやったら分かる?
レントゲン検査では股関節唇損傷の有無はわからず、確実に見極めるにはMRI検査が有効とされています。
股関節が痛くて整形外科を受診し、レントゲン検査を受けるも、「骨に異常は無い」と言われる方も多い。
股関節唇損傷を放置するとどうなる?
股関節唇損傷が進行し軟骨の傷みが悪化すると、変形性股関節症になることもある。
股関節唇損傷は手術しないといけない?
股関節唇損傷と診断されても、すぐに手術が必要になるわけではありません。
保存療法を一定期間試みても改善が見られない場合に、手術を検討するケースが多い。
なので、症状や担当医の見解にもよりますが股関節唇損傷と診断されて直ぐに手術というわけではなく、一定期間は保存療法で様子を見て改善が見られない場合、手術へと進むのが多い。
股関節唇損傷は治る?
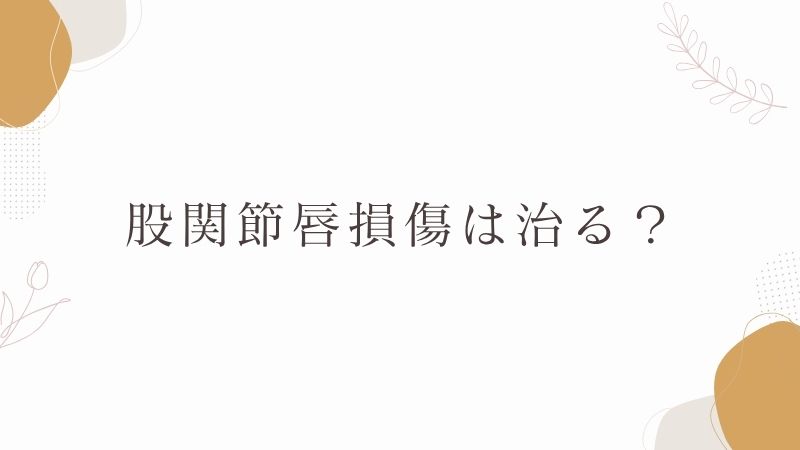
股関節唇の損傷は自然には修復しないとされています。
保存療法で治る場合と手術が必要な場合
股関節唇損傷は、症状の程度や生活スタイルによって治療法が変わります。
●保存療法(手術しない治療)
股関節周囲の筋力トレーニング、ストレッチ、姿勢改善、生活習慣の見直しなどで症状が軽減するケースがあります。実際には40歳以上では多くの人で股関節唇損傷が見られると言うデーターがあります。しかし、症状を伴わない人もいます。なので、初期症状の場合は、まず保存療法から始めるのが一般的です。
●手術が必要な場合
保存療法を一定期間試みても症状が改善しない場合や、MRI検査で大きな損傷が確認された場合、股関節鏡視下手術(関節鏡手術)が検討されます。
治療期間はどれくらい?目安と注意点
保存療法を選んだ場合、痛みや違和感が落ち着くまでの期間は3か月〜6か月が目安とされています。
ただし、筋力トレーニングやストレッチをしっかり行わないと回復が遅れることもあります。
手術を受けた場合は、術後リハビリを含めて3か月〜半年以上かかることが多く、スポーツ復帰を目指す場合はさらに時間がかかるケースもあります。
股関節唇損傷の保存療法
股関節唇損傷の保存療法のポイントは、次の通りです、
●過度の安静
股関節をかばって、安静にし過ぎると股関節を支える筋肉や靭帯が弱ります。
●正しい姿勢
猫背や反り腰は、股関節唇にストレスを与えるため、背筋を伸ばし骨盤を立てた姿勢を意識しましょう。
●靴選び
クッション性が高く安定感のある靴(例:ニューバランスのウォーキングシューズなど)を選ぶことで、股関節への負担を減らすことができます。
●インナーマッスル強化トレーニング
→ 呼吸や運動連鎖などを意識して股関節周囲の安定性を高めましょう。
●可動域改善ストレッチ
→ 腰骨の柔軟性を高め、股関節関節への負担を軽減します。
関連動画:室伏広治氏のエクササイズ
運動療法の効果的な進め方
運動療法は、焦らず段階的にステップアップしていくことが大切です。
- 初期:痛みが強い時期は日常生活+αで、体を動かすことに慣れていきます。
- 中期:インナーマッスル強化や軽いウォーキングで股関節の安定性を高めます。
- 後期:長距離の歩行、スポーツ動作の再獲得を目指します
このように、運動療法を正しく進めることで、股関節唇損傷の痛みや違和感を軽減し、再発予防にもつながります。
股関節唇損傷Q&A|よくある質問に答えます

股関節唇損傷に関して、よくいただく質問をまとめました。ここでは、治るまでの期間、運動の継続の可否、再発リスクについて詳しく解説します。
Q,運動を続けても大丈夫?
股関節唇損傷と診断されても、必ずしも運動を中止する必要はありません。
- 痛みが強い場合は、まず安静を心がけましょう。
- 痛みが落ち着いてきたら、医師や理学療法士の指導のもと、インナーマッスル強化やストレッチ、ウォーキングなどの軽い運動から始めるのがおすすめです。
ただし、ジャンプや捻り動作など股関節に大きな負荷がかかる運動は控えるようにしましょう。無理な運動はかえって痛みを悪化させる原因になるため注意が必要です。
Q,再発のリスクはある?
股関節唇損傷は、痛みが軽減しても再発するリスクがあります。
特に次のような場合は要注意です。
- スポーツや仕事で股関節に強い負担がかかる場合
- インナーマッスルの筋力が十分に回復していない場合
- 日常生活で負担のかかる動作(しゃがむ、あぐらをかくなど)を繰り返す場合
再発予防のためには、運動療法で股関節周囲の筋力をしっかりと鍛え、日常生活でも姿勢や動作に気をつけることが大切です。
もし股関節に違和感や痛みが戻った場合は、早めに医師や専門家に相談しましょう。
まとめ
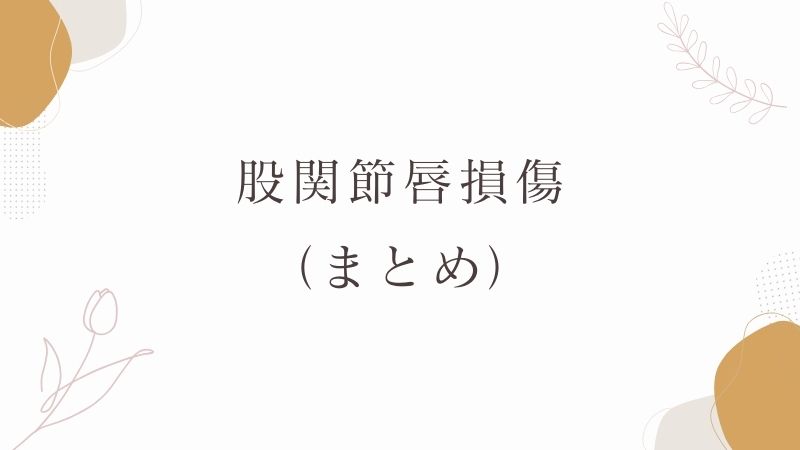
この記事では、「股関節唇損傷の原因・症状・治療法」について、整体師の視点から分かりやすく解説しました。
要点をまとめると以下の通りです。
- 股関節唇は股関節の安定を支える軟骨であり、損傷すると引っかかり感や痛みが出る。
- 原因は、スポーツや繰り返しの負荷、臼蓋形成不全、筋力低下、姿勢の乱れなど多岐にわたる。
- レントゲンでは判別できず、MRIでの診断が必要。放置すると変形性股関節症に進行することもある。
- 治療は、保存療法(姿勢改善・運動療法・靴選び)からスタートし、必要に応じて手術も検討される。
- 運動は痛みの程度に応じて段階的に再開可能。再発予防のためには、インナーマッスルの強化が鍵。
また、ニューバランスなどの安定感とクッション性に優れた靴を取り入れることで、日常の歩行時に股関節への負担を軽減できます。
違和感が長引く場合は自己判断せず、整形外科での正確な検査と適切な対応を心がけましょう。
この記事の執筆者
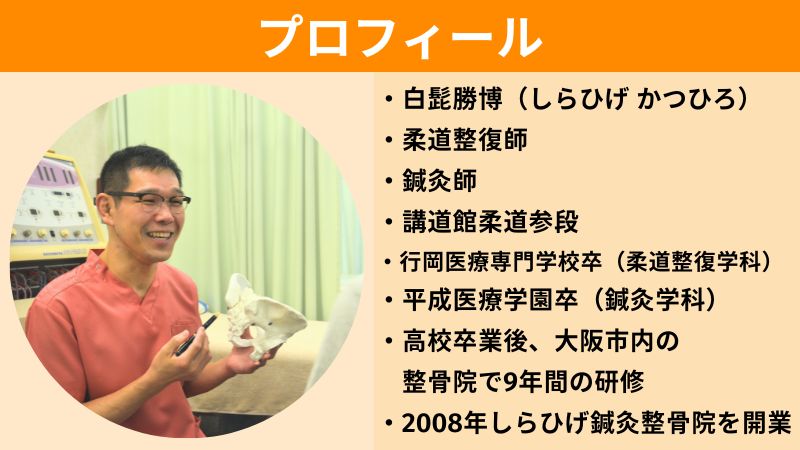
詳しいプロフィールはこちらをご覧ください→自己紹介