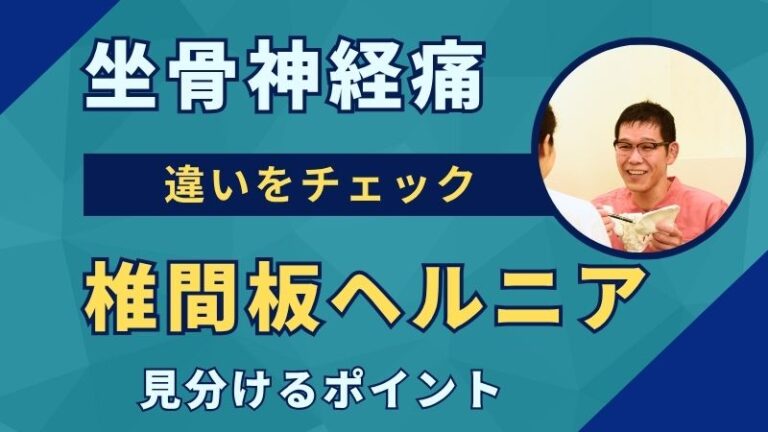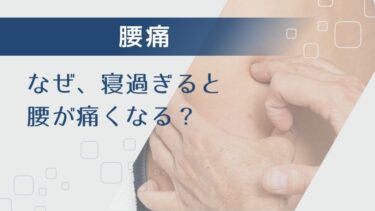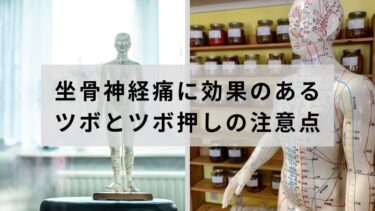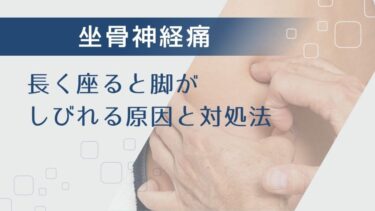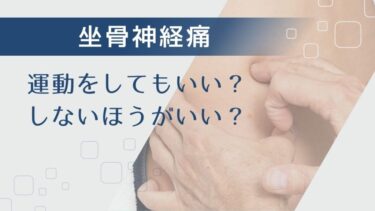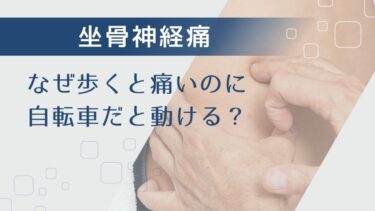- 坐骨神経痛と椎間板ヘルニアって何が違うの?
- 坐骨神経痛の対処法は?
- 坐骨神経痛はどんなことに気をつけたらいい?
坐骨神経痛と腰椎間板ヘルニアに違いは、次の通りです。
●坐骨神経痛と腰椎間板ヘルニアの違い
- しびれや痛みの感じ方
- 年齢
- 寝て脚を上げる
- 楽になる姿勢
正確にはMRIの精密検査をして、腰骨や椎間板の状態を確認しないといけないと言うことを前置きにします。
突然、「脚にしびれ」が現れると、これは「腰のヘルニアかな?」「ヘルニアって手術をしないといけないのかな?」と心配になりますよね。
そんな時の不安が少しでも減るように分かりやすく解説していきますので、ぜひ、最後まで読んでください。
それでは、さっそく見ていきましょう。
しびれや痛みの感じ方の違い
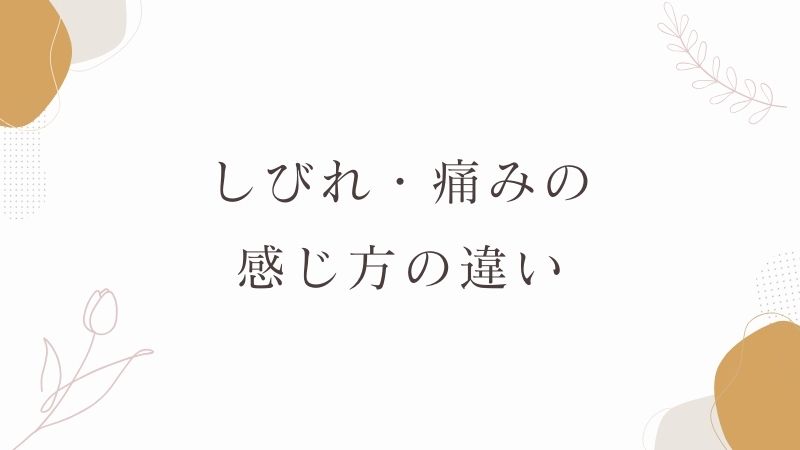
坐骨神経痛と腰椎間板ヘルニアでは、しびれや痛みの感じ方に違いがあります。
具体的には坐骨神経痛では、痛みや痺れが不定期に現れるのに対して、腰椎間板ヘルニアでは、常に痛みやしびれがあります。
特に腰椎間板ヘルニアでは、座っているときも寝ている時も常に症状があります。
常に痛みやしびれがある場合は、腰椎間板ヘルニアを疑いましょう。
年齢による違い
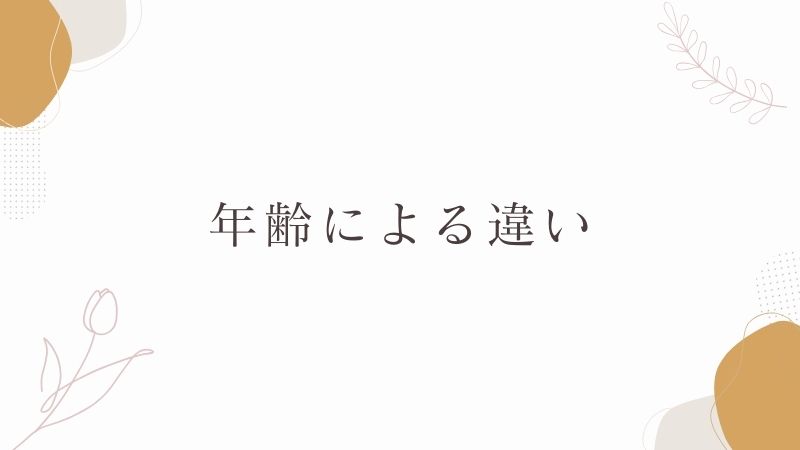
坐骨神経痛と腰椎間板ヘルニアを見分けるポイントに、年齢があります。
具体的には、椎間板というのはゼリーのように「ぷにゅぷにゅ」しています。
これは水分が潤っているからです。
しかし、年齢が過ぎると、身体の水分が減少し椎間板は、ゼリーから高野豆腐のようにカチカチになっていきます。
高野豆腐のように、カチカチの状態では、椎間板が飛び出ることは少なくなります。
つまり、腰椎間板ヘルニアは若い世代に多いということ。
私の経験上10〜30代はヘルニアを起こしやすい傾向があります。
寝て脚を上げる
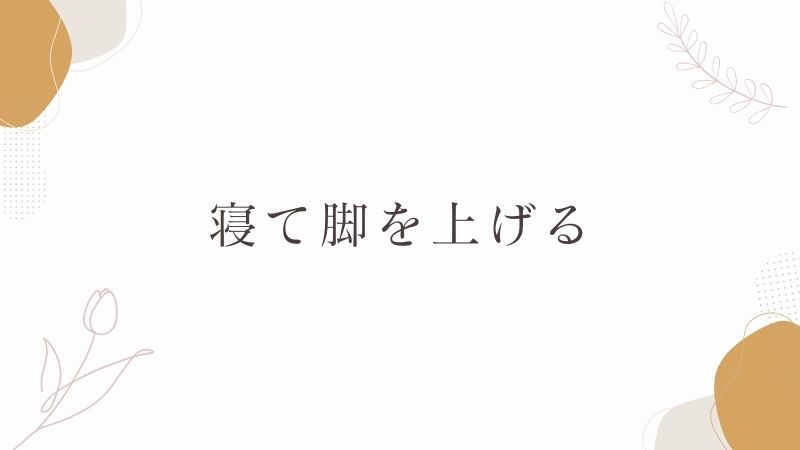
坐骨神経痛と腰椎間板ヘルニアを見分けるポイントに、寝て脚を上げる方法があります。
これは、MRIなどの機械を使わずに、外から見分ける検査方法として病院内でも行われます。
●やり方
- 仰向けに寝る。
- 症状がある方の脚を、膝を伸ばしたまま上げる。
- 角度は70°ほどで症状が強くなればヘルニアを疑う。
腰椎間板ヘルニアでは、脚上げ検査をすると、明確なしびれが現れます。
楽になる姿勢
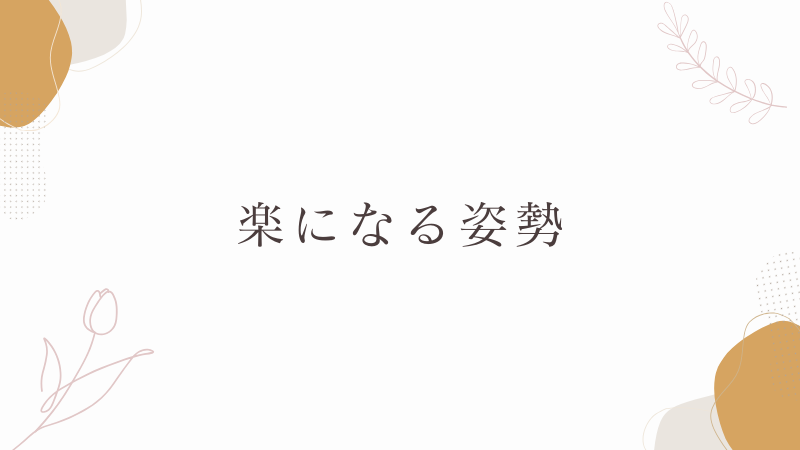
坐骨神経痛と腰椎間板ヘルニアを見分けるポイントに、楽になる姿勢があります。
座っていると楽、歩くと痺れが出てくる、少し休むんだり前屈みになると楽になる。
この場合は、坐骨神経痛でも腰椎間板ヘルニアでも無く脊柱管狭窄症の可能性があります。
脊柱管狭窄症は、60歳以降に多くみられる傾向があります。
▶︎関連記事:脊柱管狭窄症について
見分けるポイントの補足
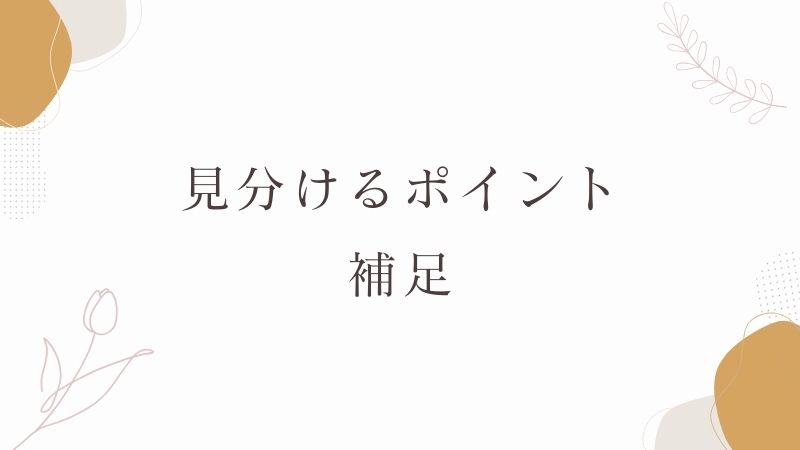
ここまで読んで頂いていかがでしたか?
今の症状が、坐骨神経痛なのか、腰椎間板ヘルニアなのか、少しは見分けがつきましたか?
補足になりますが、ここでの解説は自己判断するものではなく、あくまで専門医にかかるまでの不安を少しでも、軽減していただければと思って書いています。
なので、症状があるのであれば早めに医療機関を受診してください。
坐骨神経痛の対処法
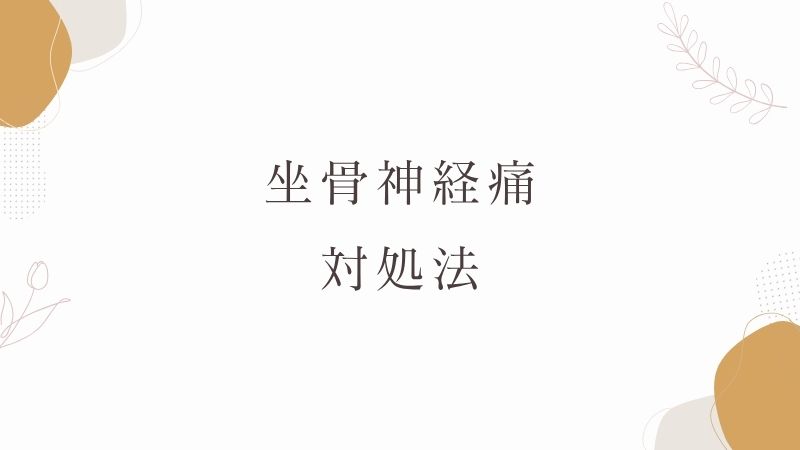
坐骨神経痛の対処法を3つ紹介します。
坐骨で座る
坐骨で座ることで、骨盤が立ち、腰にかかる負担が軽減されます。
坐骨とは、椅子に座った時にお尻の真下に手を入れて、当たる骨です。
また、良くない座り方を「仙骨座り」と言います。
仙骨座りは、腰にもの凄く負担がかかる座り方で、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症の原因にもなります。


▶︎関連記事:腰に負担をかけない座り方
腰伸ばし運動
腰伸ばし運動は、背骨の柔軟性を回復させる運動です。
日常生活では「前かがみ」になることは多いですが、後ろに反りかえることは、ほとんどありません
すると、背骨のしなりが無くなり腰に負担がかかります。
また、猫背や巻き肩の原因にもなります。
なので、背骨のしなりを回復し保つのに、腰伸ばし運動がおすすめです。
▶︎関連記事:腰・背中の硬さを解消するストレッチ
ハイハイ運動
ハイハイ運動には、次のような効果があります。
- 背骨の柔軟性の回復
- インナーマッスルの強化
- 運動連鎖のトレーニング
- 肩甲骨の運動
- 手足の連動運動
赤ちゃんは、ハイハイ運動で体幹を強くして、立つようになります。
体幹がしっかりとすることで、腰にかかる負担が減り、坐骨神経痛、腰痛予防になります。
▶︎関連動画:ハイハイ運動
坐骨神経痛で気をつけること
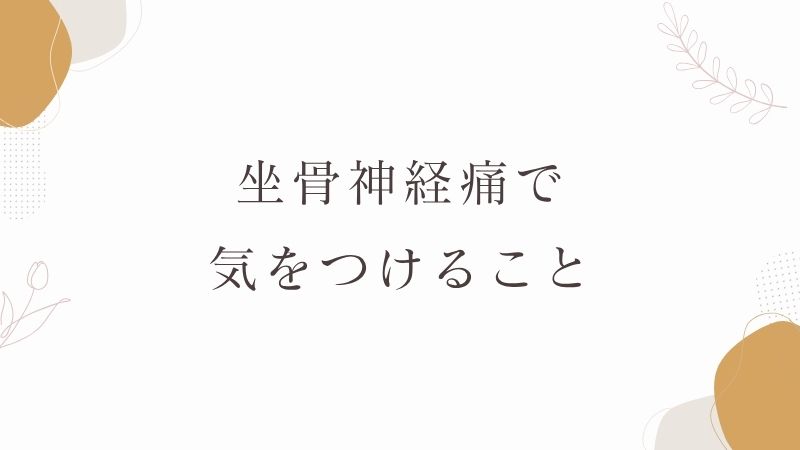
坐骨神経痛では、次のことに気をつけましょう。
- 座り方
- 過度の安静
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
座り方
坐骨神経痛の原因はさまざまですが、私が臨床の現場で感じるのは、「座り方の問題」が非常に多いです。
時代背景として、デスクワークが増えているのもあるでしょう。
だからこそ、坐骨神経痛の改善にも予防にも座り方は、とても大切です。
ぜひ、上記でお話しした、坐骨座りを意識してみてください。
▶︎関連記事:デスクワークと坐骨神経痛
過度の安静
坐骨神経痛で痛みやしびれがあるからと言って、過度の安静にならないようにしましょう。
過度の安静にすることで、背骨を支える筋肉や靭帯が弱り、さらに負担がかかり、悪循環になります。
もちろん、痛みやしびれが強い時は、一時的に安静が必要な時もあるでしょう。
安静にし過ぎるデメリットもしっかりと理解していきましょう。
ちなみに、強い痛みやしびれが続く場合は、我慢をせずに医療機関を受診しましょう。
坐骨神経痛と腰椎間板ヘルニアの違いは?(まとめ)
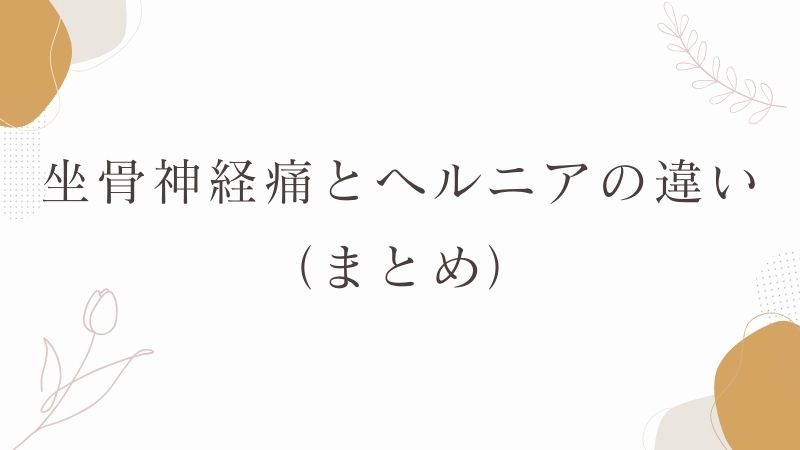
この記事では、「坐骨神経痛と腰椎椎間板ヘルニアの違い」や「坐骨神経痛の対処法・注意点」について詳しく解説しました。
要点を整理すると、以下のようになります。
- 坐骨神経痛は体勢で神経が刺激されるが、ヘルニアは常に神経が圧迫されている
- ヘルニアは若年層に多く、坐骨神経痛は年齢を問わず起こる
- 坐骨神経痛の対処には「坐骨で座る・腰伸ばし運動・ハイハイ運動」がおすすめ
- 座り方の見直しや過度な安静を避けることも重要な対策
坐骨神経痛は、姿勢や体の使い方の改善によって、症状の緩和が期待できるケースも多くあります。
痛みやしびれが続く場合は無理をせず、専門医を受診して正しい診断と適切な治療を受けましょう。
この記事の執筆者
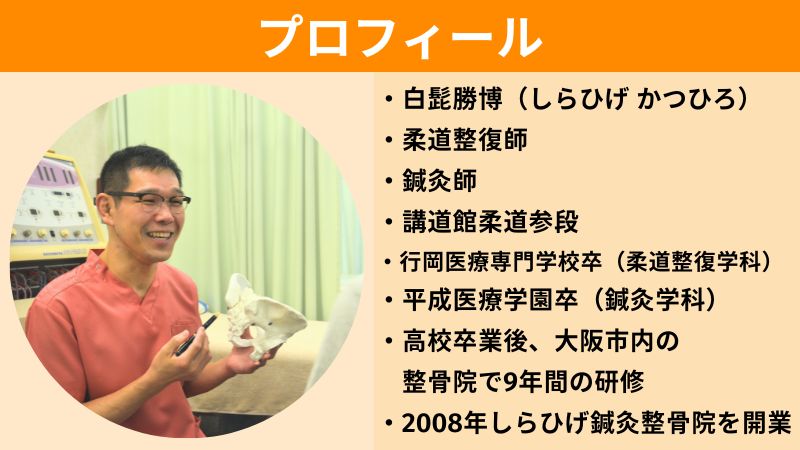
詳しいプロフィールはこちらをご覧ください→自己紹介