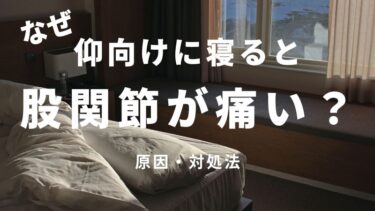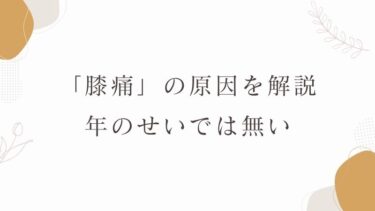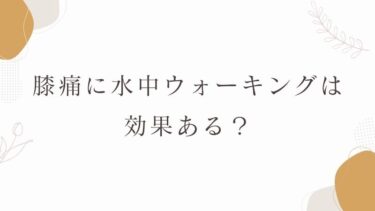- 膝痛はどんな症状が出る?
- 膝からスネにかけて痛い。
- 膝がパキパキと鳴る。
こんな、お悩みありませんか?
何となくの膝の違和感…、もしかすると「膝痛」の初期症状かも知れません。
放置すると進行し、変形性膝関節症や半月板損傷の原因んいなることもあります。
この記事では、膝痛の症状について解説します。
膝痛の症状を正しく理解すれば、日常生活の負担を減らす第一歩になりますので、ぜひ最後までお読みください。
それでは、さっそく見ていきましょう。
膝痛の症状
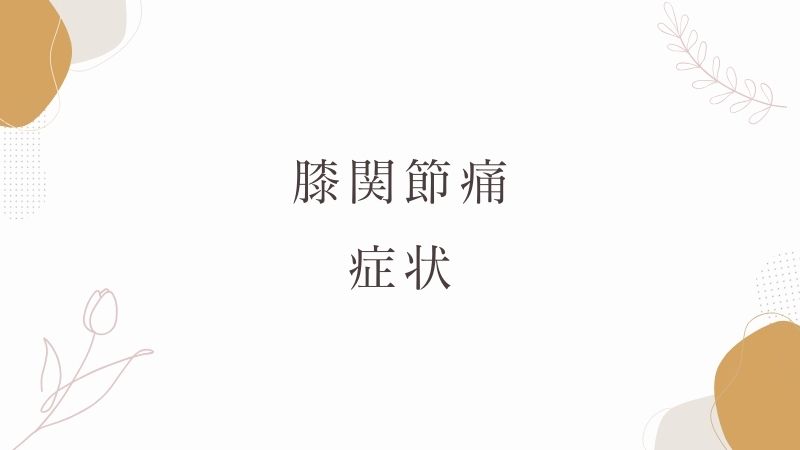
膝関節痛では、次のような症状が起きます。
- 膝の内側の痛み
- 太ももの外側の痛み
- すねの痛み
- お皿の下の痛み
- 膝裏の痛み
- パキパキと音が鳴る
それぞれ、詳しくみていきましょう。
膝の内側の痛み
膝の内側の痛みは、変形性膝関節症で起きやすい症状。
変形性膝関節症では、内側の軟骨がすり減りやすいために、膝の内側に痛みが起きやすいです。
軟骨がすり減ると、骨と骨が擦れてやがて骨が棘のように尖っていきます。
この尖りを「骨棘」と言います。
骨棘は、関節包や筋肉を刺激し、炎症を起こし痛みの原因になります。
太ももの外側の痛み
太ももの外側の痛みは、猫背・腰が曲がっている人に起きやすい症状です。
猫背や腰が曲がると、「骨盤は後傾」します。
骨盤が後傾すると、股関節が開き、いわゆる「ガニ股」になります。
ガニ股になると、足の外側に体重をかけて歩くので、太ももの外側の筋肉に、ものすごく負担がかかります。
なので、猫背・腰が曲がっている人は、太ももの外側に痛みが起きやすいです。
すねの痛み
すねの痛みは、上記の太ももの外側の痛みと、合わせ持つことがいです。
すねの中でも、膝近くの外側・丸い骨の出っ張りに、痛みが起きやすいです。
上記でお話しした、ガニ股で歩いた時に、すねの膝近く外側・丸い骨の出っ張りに、体重がかかり痛みが起きます。
長年にわたり、ガニ股の人は、丸い骨の出っ張りが、目立つぐらい変形している場合もあります。
お皿の下の痛み
お皿の下の痛みは、前体重で歩く人に起きやすい症状です。
⚫️前体重で歩く人の特徴は次の通り。
- 高さのある靴を履く。
- 過去長年に渡り高さのある靴を履いていた。
- 硬いインソールを入れている。
- 杖をつく。
- 押し車を使う。
中でも、高さのある靴は、2〜3cmでも、長年履いていると、徐々に前体重の歩行になっていきます。
また「靴に高さがないとしっくりこない」「高さがないと違和感」と感じる人は、高さのある靴が習慣になっているので、注意です。
膝裏の痛み
膝裏に痛みが起きやすい人は、次の通りです。
⚫️膝裏に痛みが起きやすい人
- 座りっぱなし
- 高さのある靴を履く
- ちょこちょこと歩く
- 膝の曲げ伸ばしをしない
膝裏の痛みは、上記の他の痛みと一緒に持つことが多いです。
また、長時間、膝を曲げていると、リンパが通る「管」が圧迫され、流れが悪くなり、膝が脹れぼったい状態になります。
リンパの流れが悪くなると、リンパが通る管の中では、「根詰まり」を起こし、さらにリンパの流れが悪くなります。
すると、膝が腫れて痛みを起こします。
寝る時に伸ばすと痛い
寝る時に膝を伸ばすと膝が痛いのは、膝が曲がった状態で、曲げ伸ばしがない人に多い症状です。
寝る時に布団で、仰向けになった時に、腰・膝が伸びず、膝の痛みを感じます。
上記の膝裏の痛みと一緒に持つことが多いです。
仰向けで寝ると、股関節がズキッと痛む… どんな姿勢で寝るのがいい? マットレスは変えた方位がいい? こんな、お悩みありませんか? 実は股関節や腰の関節は、長[…]
パキパキと音が鳴る
パキパキと音が鳴るのは、膝のお皿が上手く動いていない人に、起きやすい症状です。
パキパキと音がなる人は、次の通りです。
⚫️パキパキと音がなる人
- 膝を着く
- 過去に膝を強く打った
- 横坐りをする
- ジャンプする競技をしていた
- 走る競技をしていた
膝の音は鳴るが、痛みは伴わないために長期間、放置され、他の症状へと進行していくこともあります。
深く曲げると激痛が走る
膝を深く曲げて、激痛が走るのは、半月板の損傷がある人に、起きやすい症状です。
半月板が損傷し膝関節の隙間に引っかかると、激痛が起きます。
また、膝の腫れも一緒に起きやすいです。
どうして膝に水が溜まる? 膝に水が溜まるとどうなる? 膝の水は癖になる? こんな、お悩みありませんか? 膝の水に関するポイントは、次の通りです。 &nbs[…]
まとめ|膝痛の症状
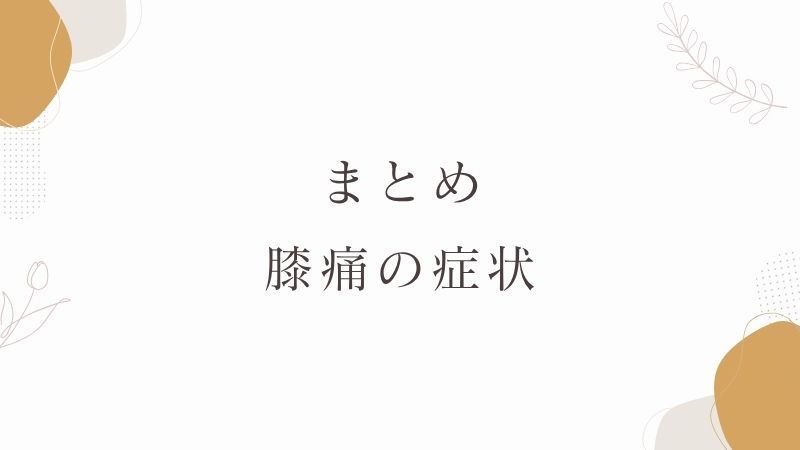
この記事では、「膝痛の主な症状とその原因」について解説しました。
要点をまとめると以下の通りです。
- 膝の痛みは場所によって原因が異なり、内側・外側・すね・お皿の下・膝裏など部位ごとに特徴がある。
- 「パキパキ音が鳴る」「深く曲げると激痛」なども膝痛のサインのひとつである。
- 猫背・前体重・ガニ股・長時間の座位など、日常の姿勢や動作のクセが症状に影響を与えている。
膝痛では、「どこが痛むか」「どんな動作で痛むか」「痛み以外の症状(音・腫れなど)」を把握することが、適切な対処の第一歩になります。
日常の違和感や「なんとなく気になる症状」も放置せず、膝痛の進行を防ぐために、早めに原因を知り、対策をとっていきましょう。
この記事の執筆者
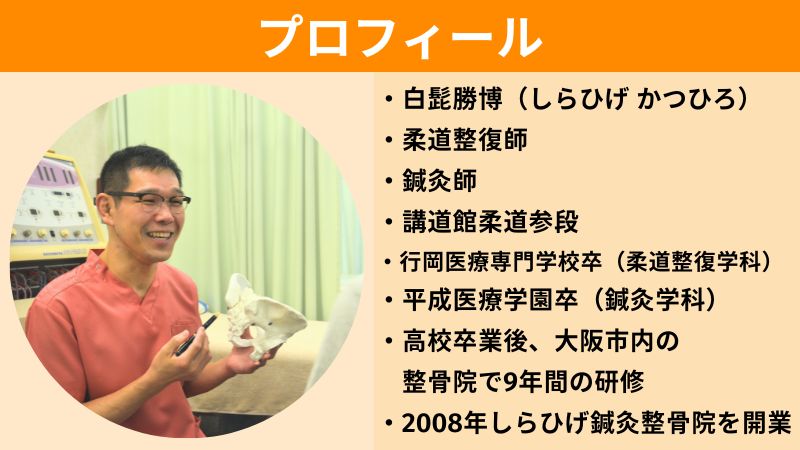
詳しいプロフィールはこちらをご覧ください→自己紹介
無理をせず、自分に合ったケアを取り入れて、快適な生活を取り戻しましょう。